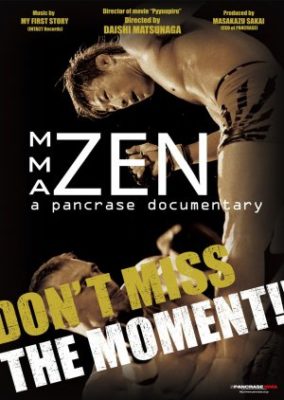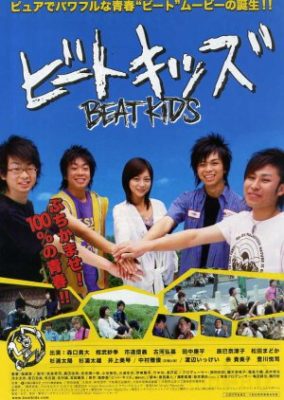ある春の日、病院のベッドに寝たきりの老女が、エミや真一ら4人の孫を呼び寄せ、自分の両親や兄弟のことを話し始める。70年前、彼女が育った家庭は、他のどの家庭とも全く違っていた。
1937年の大阪、鈴木重三郎は大阪理科大学の助教授で植物学者であった。10年連れ添った明るく優しい妻・聖子との間には、子宝に恵まれることはなかった。しかし、重三郎はそれを受け入れ、夫婦仲は良好であった。しかし、聖子の母親願望は消えなかった。重三郎の姉、大沢典子の息子で満州に赴任する和也の送別会をきっかけに、子供が欲しいという気持ちが強くなっていった。
数日後、間宮君子が経営する養護施設の庭で遊ぶ子供たちを見て、聖子は重三郎に孤児を養子にすることを相談します。当初は子育てに自信がないと言っていた重三郎だったが、彼女の熱心さに押され、幸太を養子として迎えることになった。幸太に優しく接する聖子に対し、重三郎はぎこちないながらも、次第に叱ったり褒めたりすることを覚え、父親として成長していく。研究のためだけに生きていた茂三郎は、新たな生きがいを見つけ、世界が一変した。幸太が笑うために、彼はただ笑えばよかったのだ。感情をほとんど表に出さない寡黙な男が、どんどん笑顔になっていった。そしてある日、「兄弟がいたら、息子は幸せかもしれない」とつぶやいた。聖子さんは、「それはすぐにでもできますよ」と答えた。
それから6年後、鈴置家は幸太、節子、健作、虎之助、留子の5人の子供を持つ大家族になっていた。やがて、茂三郎の研究助手だった吉田四郎が徴兵され、太平洋戦争が茂三郎の周囲にも影響を及ぼすようになった。鈴 木夫妻の生活は、ますます苦しくなっていった。それでも、重三郎と聖子は笑顔を絶やさず、子供たちも笑顔で過ごしていました。しかし、戦争は一家の将来に着実に影を落としていった。
(出典:jdramas.wordpress.com)